映画一揆2025 時代が終わり 時代が始まる 上映作品解説

第一アパート
1992年/58分/8mm→デジタルリマスターDCP
出演:吉岡文平 本田孝義 高橋和博
遠藤葉子
監督:井土紀州 吉岡文平
脚本:井土紀州
撮影:高橋和博
録音:菊地忠敬
製作:映像集団バイマツ
主人公の男は正体不明の不安と頭痛に悩まされている。その謎を解く鍵は、男が幼少期を過ごした場所にあった。 男は謎を解明するため故郷に向かうのだが、果たしてそこには何があるのか……。 未知の場所に深く深く入り込んでいくカメラ、奇妙な夢、 魚の死骸、古いレコード、朽ちていく土地……。 様々なモチーフがモノクローム・パートカラーの映像で重層的に描かれていく。 未整理ながら、確実に『百年の絶唱』への飛躍を予感させる作品である。 1992年の上映時には、映画が内包する可能性と独創性を崔洋一や青山真治らに絶賛された。

百年の絶唱
1998年/87分/8mm→16mm
出演:平山寛 葉月螢 佐野和宏
坪田鉄矢 加藤美幸
監督・脚本:井土紀州
撮影:西原多朱
追加撮影:高橋和博
照明:伊藤学
助監督:馬見塚仁
製作:吉岡文平・中澤純子
プロデューサー:松岡亮
題字:翠川英人
製作:スピリチュアル・ムービーズ
中古レコード屋でアルバイトをしながら別れた女のことが忘れられず虚ろな日々を送っている青年平山。 失踪した男が残したレコードを引き取ってくれという依頼に、その部屋を訪れた平山はこの世のものとは思えぬ異様な声を聞く。 それが全ての始まりだった。徐々に彼の周りで異変が起こり始める。レコードを返せと付きまとう女、抜けた歯、血痕を這うなめくじ、廃墟の小学校、ダムの底に沈む村……。 やがて、平山に失踪した男の記憶が浸透し始める。もう誰の記憶かわからない。平山はつき動かされるようにある目的に向かって行動を起こした・・・・・・。 1998年に劇場公開され、スピリチュアル・ムービーズの名を世に知らしめた渾身の一作。

ヴェンダースの友人
2000年/75分/デジタルリマスターDCP
出演:山本均 高岡茂 光山明美
豊川忠宏
監督:井土紀州
制作・撮影:吉岡文平
撮影協力:伊藤学
編集オペレーター:加藤智陽
編集スタジオ:boid
写真撮影:曽木幹太
製作協力:スローラーナー 福岡市総合図書館
製作:スピリチュアル・ムービーズ
ヴィム・ヴェンダースの幻の初期作品『三枚のアメリカのLP』が一日だけ東京で上映された。そこで井土は、年長の友人山本均と10年ぶりの再会を果たす。 その後、井土は大阪に住む山本を訪ね、彼の映画三昧の日々にカメラを向ける。 ヴェンダースが映画で使用した音楽を集めて編集テープを作るという山本の執念の作業や、 ある映画がいかにして自分の人生と交錯したかについて語る山本の情熱は圧巻である。 劇場未公開だが、ここでの方法論が次作『LEFT ALONE』へと展開していったことが分かる。

『LEFT ALONE 1』
『LEFT ALONE 2』
『LEFT ALONE 1』2005年/93分/
デジタルリマスターDCP
『LEFT ALONE 2』2005年/109分/
デジタルリマスターDCP
『LEFT ALONE 1』出演:
絓秀実 松田政男 西部邁 柄谷行人 鎌田哲哉
『LEFT ALONE 2』出演:
絓秀実 松田政男 柄谷行人 津村喬 花咲政之輔
監督:井土紀州
ナレーション:伊藤清美
製作:吉岡文平
撮影:伊藤学 高橋和博
音楽:太陽肛門スパパーン
整音:臼井勝
企画・製作:スピリチュアル・ムービーズ
2001年に早稲田大学で勃発したサークルスペース移転阻止闘争において、当時非常勤講師だった絓秀実は学生たちと一緒に大学と闘うことになる。 映画は、そんな絓の姿を追いかける一方で、かつて活動家だった知識人たちとの対話を通して、日本の新左翼史を浮かび上がらせる。 ニューレフトの誕生、60年の安保闘争、花田清輝と吉本隆明の論争、68年革命の思想と暴力、ゼロ年代の大学再編と自治空間の解体など、様々な話題を松田政男、西部邁、 鎌田哲哉、柄谷行人、花咲政之輔といった活動家や批評家たちと討議する。 特筆すべきは、絓の“68年革命論”の核心をなす人物、津村喬を滋賀県に訪ねる場面で、そこでの対話はスリリングであると同時に感動的である。 近年、本作は日本のニューレフト運動史の入門書として注目を集め、海外の研究者からの問い合わせも多い。

ラザロ -LAZARUS-
「蒼ざめたる馬」篇
2007年/40分/デジタルリマスターDCP
出演:東美伽 弓井茉那 成田里奈
大沼幸司
監督:井土紀州
撮影:鍋島淳裕
音楽:花咲政之輔 太陽肛門スパパーン
題字:翠川英人
製作:スピリチュアル・ムービーズ
京都国際学生映画祭2003運営委員会
資産家の子息を狙ってたぶらかし、殺害した後に相手の預金を奪って、共同生活を送る三人の女たち。 リーダーのマユミは言う。「金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏になる。それがこの社会のカラクリや」と。 不幸な生い立ちのミズキとリツコは、マユミに操られるまま、犯罪に加担していく。 だが、一番年下のミズキは、だまして殺すはずの相手・陽介のことを好きになり始めていた。ミズキとマユミの間に生まれた亀裂は次第に大きくなっていく……。 明確な階級意識にもとづいて、次々と犯罪を遂行していく女、マユミ。その非情さは見る者を震撼させる。

「複製の廃墟」篇
2007年/80分/デジタルリマスターDCP
出演:東美伽 池渕智彦 小野沢稔彦
監督:井土紀州
撮影:鍋島淳裕
音楽:花咲政之輔 太陽肛門スパパーン
題字:翠川英人
製作:スピリチュアル・ムービーズ
「よかったら使ってください」と言わんばかりに、ポストに投函される大量の一万円札。生活が困窮した者ならば、迷うことなくそのお金を使うだろう。しかし、それが本物か贋物か分からないくらい精巧な贋札だったとしたら……。 本作でのマユミは相棒のナツエと共に贋札を首都圏一帯にバラまいていく。そうやって、ハイパーインフレを起こして日本経済を壊滅させようというのだ。手本にしたのは戦時中に日本陸軍が行った贋幣作戦。 贋札犯を追う刑事たちは、日本近代史の闇からよみがえった亡霊と対峙していくことになる。

「朝日のあたる家」篇
2007年/81分/デジタルリマスターDCP
出演:東美伽 堀田佳世子 小田篤
監督:井土紀州
撮影:鍋島淳裕
音楽:花咲政之輔 太陽肛門スパパーン
録音:小林徹哉
題字:翠川英人
製作:スピリチュアル・ムービーズ
伊勢映画人会
ここで語られるのはマユミ前史である。彼女はとある地方都市で生まれ、事務の仕事をしながら、今も地元で暮らしている。マユミの実家は商店街で衣料品店を営んでいたが、現在は閉店してシャッターを閉ざしている。商店街自体にも活気はなく、いわゆるシャッター商店街となっている。地元に、郊外型の巨大なスーパーが出来たことが、商店街が寂れた原因の一つだったが、今、マユミはそのスーパーの社員・梶川と交際していた。そこに、東京で夢破れた妹のナオコが帰ってくる。 マユミが梶川と付き合っていると知ったナオコは激怒する。「うちの商店街が寂れたんは全部あいつらのせいや!」と。 マユミはナオコを説得し、梶川もまたナオコに対して誠実に対応するが、埋めようのない格差がナオコを思いもよらぬ行動に駆り立てていく。 2007年に公開され、一時代の血を沸かせた「ラザロ」完結篇。
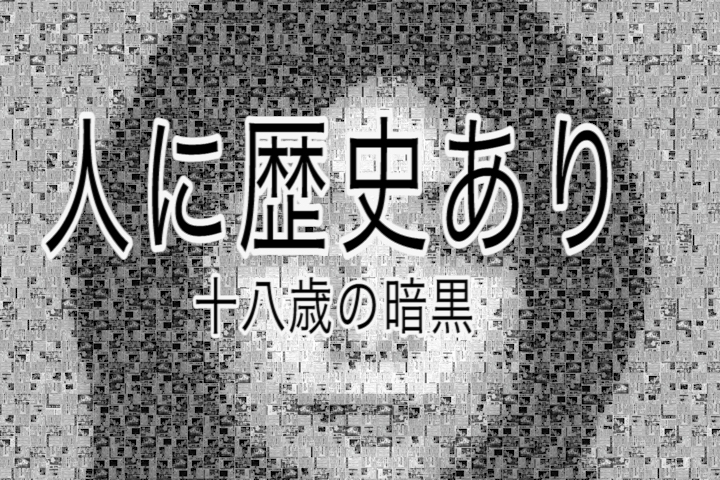
人に歴史あり~十八歳の暗黒
2008年/10分/デジタルリマスターDCP
監督:井土紀州
編集:谷脇邦彦
録音:近藤崇生
第3回ガンダーラ映画祭に向けて2008年に製作された短篇作品。カメラなし撮影なし、という異色作に井土の妄想力が炸裂する。 整形逃亡犯・福田和子と品川同性愛者殺人事件の前田優香、新聞や雑誌など膨大な資料を駆使しながら、映画はこの二人の犯罪に迫っていく。 その人物はなぜ“一線を越えた”のか? その人物にとって”躓きの石”は何だったのか? それを探っていく姿勢からは、実際の事件をモチーフにしてフィクションを生み出してきた井土の方法論が垣間みえる。

行旅死亡人
2009年/112分/デジタルリマスターDCP
出演:藤堂海 阿久沢麗加 たなかがん
本村聡 長宗我部陽子
監督・脚本:井土紀州
企画:上野昻志 柳沢均
撮影・照明:伊藤学
録音:小林徹哉
音楽:安川午朗
制作担当:桑原広考 吉川正文
プロデューサー:沼口直人 吉岡文平
製作協力:スピリチュアル・ムービーズ
製作:日本ジャーナリスト専門学校
題字:翠川英人
十五年もの間、他人の名を騙り、自分が何者であるかを明かすことなく死亡した男の事件をもとに構想されたミステリー。 滝川ミサキは、アルバイトをしながらノンフィクション作家を目指している。ある朝、そんなミサキの元に「滝川ミサキさんが倒れました」と病院から電話が入る。ミサキは、何かノンフィクションのネタになるかもしれないと病院に駆けつけると、そこには意外な人物の姿があった。やがて、ミサキの名を騙った女は自分の身元を明かすことなく亡くなってしまう。 彼女は何者だったのか? 真相を探るミサキの前に、女の謎めいた人生が立ちはだかるのだった。 ある女の存在証明というテーマに取り組んだ映画で、井土が敬愛する松本清張や橋本忍の影響が随所に見られる。

犀の角
2009年/53分/デジタル
出演 櫻井拓也 富岡英里子 吉岡睦雄
長宗我部陽子
監督:井土紀州
脚本:川﨑龍太
撮影監督:鍋島淳裕
録音:福田伸
美術:坂本千斗
助監督:川﨑龍太
制作担当:桑原広考
プロデューサー:山本隆世 加瀬愼一
協力プロデューサー:吉岡文平
制作協力:スピリチュアル・ムービーズ
企画・製作:日本映画学校
高校生・鈴江崇が住む町に、「カフ・サマージ」と称する宗教団体が移住してきた。謎めく教団の活動に、地元住民は警戒心を強めていく。ひょんなことから崇は信者である少女と交流を重ねる。少女の抱える心の闇に触れ、次第に惹かれていく崇。一方、教団に対する住民たちの嫌がらせは日を追ってエスカレートしていくのだった。 当時、日本映画学校(現・日本映画大学)俳優科の学生だった富岡英里子と三十一歳で早逝した櫻井拓也のみずみずしい演技が胸を打つ。また、元信者で現在は教団排斥の急先鋒にたつ男を吉岡睦雄が怪演しており、この人物には日本人のある典型をみることが出来る。

土竜の祭
2009年/50分/デジタル
出演:ほたる 長宗我部陽子 阿久沢麗加
監督:井土紀州
撮影:木暮洋輔
照明:高井大樹
録音:臼井勝
音楽監督:平山準人
助監督:川口陽一
制作:佐野真規 冨永威允
協力プロデューサー:吉岡文平
制作協力:スピリチュアル・ムービーズ
製作:映画美学校
おっちょこちょいでお金にルーズな朝子。クールでどこか陰のある霞。能天的で生意気な千晴。彼女たちは訪問介護を請け負うヘルパーだ。わいわい、いつもの様に賑やかに仕事をしていると、 担当する熊谷老人からお金を振り込んで来てくれないかと頼まれる。そのお金の振込先は、不可解なものだった。真相を探り始めた三人の前に、意外な人物が姿を現す。それは霞にとって絶対に会いたくない相手だった……。 今を懸命に生きる者の前に、忘れたい過去が亡霊のように姿を現す、という井土がこだわってきたモチーフがこの映画でも変奏される。高齢化社会、特殊詐欺、先物取引、賭博といった題材をユーモラスに描いたブラックコメディ。

泥の惑星
2010年/53分/デジタル
出演:千葉美紅 上川原睦 小林歩祐樹
監督:井土紀州
脚本:天願大介
撮影:高橋和博
照明:吉川慎太郎
録音:岩丸恒
音楽:平山準人
助監督:川﨑龍太
制作:吉川正文 冨永威允
プロデューサー:天願大介 加瀬愼一
協力プロデューサー:吉岡文平
制作協力:スピリチュアル・ムービーズ
企画・製作:日本映画学校
農業高校に通うハルキ達は毎日泥まみれになってレンコンを収穫し、なんとなく楽しく過ごす日々。 「ずっとこんな感じだったら、それって幸せかな。不幸かな」 そんな問いにも答えられないある日、ハルキは天文部の転校生、アキに一目惚れしてしまう。 そうして回り始めたハルキの歯車につれられるようにして、仲間達の歯車もまた回り始める。一方、校内の植物は原因不明のまま枯れ始め……。 「今ある星座を破壊せよ。星と星の間に、新しい一本の線を引け」 彼らに、新しい線は引けるのか。 天願大介による脚本を井土が監督した異色の青春映画。

漂着物
2017年/32分/DCP
出演:細江祐子 本多章一
監督:井土紀州
脚本:小谷香織 井土紀州
撮影:高橋和博
照明:俵謙太
録音:中川究矢
ドローン撮影:上田茂
俗音:近藤崇生
題字:翠川英人
編集:桑原広考
助監督:遠藤晶
プロデューサー:吉岡文平
製作:スピリチュアル・ムービーズ
202X年、東京オリンピックの喧騒は過ぎ去り、様々な廃墟と凄まじい量の廃棄物が残された首都・東京。都心から吐き出された多くのゴミは 潮の流れに乗って東京湾の片隅に流れ着いていた。西澤修也は、海辺の廃墟に住みつき、流れ着いたゴミを拾って生計を立てている。 隠遁者のように暮らす修也の生活圏に、一人の女・咲が迷い込んできた。言葉を交わし、触れ合ううちに、次第に明らかになる二人の過去。 それはのっぴきならぬ事態に二人を追い込んでいくのだった。

雲がくれ
2025年/40分/DCP
出演:竹内香帆 前田瑞貴 小田篤
脚本・監督:井土紀州
撮影:高橋和博
照明:俵謙太
録音:小濱匠
ヘアメイク:久野由喜
音楽:高橋宏治
助監督:登り山智志
監督助手:相原柊太
制作デスク:野崎芳史
演出応援:遠藤晶 小谷香織
制作応援:増田加奈 堀三郎
題字:翠川英人
編集:桑原広考
整音:小濱匠
美術協力:佐々木愛
特別協力:坂口一直
プロデューサー:吉岡文平 桑原広考
製作:スピリチュアル・ムービーズ
あずさは連絡が取れなくなった彼氏の元カノのアパートを訪ねると、留守らしく応答はない。諦めて帰ろうとすると、彼氏が着ているはずの 服を着た男を見かける。どうしても彼氏の居場所をつきとめたいあずさはその男に頼み込み、大家とともに彼氏の元カノの部屋に入った。 そして、3人がそこで見つけたものは…。